IC-1275 の修理再び⑥
さて今度は送受信の不具合と内蔵電源のお話しから。
ある日、出張から帰り、IC-1275の電源をONにすると、ONになった途端OFFに。電源ボタンをON/OFFしても当然ONにならない。また逝ってしまったのかと、ちょっとめんどくさいなと思いつつ最低限の確認をした。(まあ、よく壊れるわ)
・電源部~電源ヒューズ→真っ黒で溶断
・もう一度新しいヒューズを入れ再度ON → やっぱり一瞬で溶断。
これはもう電源だなと言う事で、電源を切り離し直接 DC でON。無事ONになりホットしたのもつかの間。送信するとなぜか送信の立ち上がりがおかしい。LOW だと VSWR が3以上。HIGHにすると、ぐっと下がり VSWRも1.0に。しかし LOW にするとおかしい・・。後々この操作が問題を起こしたんですが・・。
IC-1275には送受信切り替え用のモジュール三菱のMD004Hが使われています。これは IC-2500の修理の時にもお話ししています。どうやらこいつが、先ほどの電源瞬断で壊れたっぽい。(かどうかは謎なのですが。)
 |
 |
 |
MD004H |
電源+送信部 |
MD004H取付部位 |
しかも、当然なんですが、このモジュールがもう製造していない。しかも日本国内何処探してもない。仕方ないので掘り出し物が出るまで、しばらく放置するこにしていたのですが、ローカルさんが 「そういえばMD004H探してたよね、ヤフオクに出てるよ」と連絡を頂きました。これは!と思いヤフオクを確認するとやはり出てます。これは買わないと。と言うことで、即決がありましたので、即決でご購入。これで治る!と息巻いたのですが、この無線機特有の更なる試練が待ってました。
 |
 |
 |
基盤を外します |
外しましたが |
MD004H取り外し |
何とかMD004Hを交換。早速電源をONにしてみました。送受信が正常に切り替わるのを確認しました。もちろん送信の立ち上がりは問題なし。パワー可変しても問題なし。LOWとHIの送受信立ち上がりも問題なし。ただ時間が時間で相手をしてくれるローカルさんも居ないので仕方なくレピーターをカーチャンクしてみることにします。ただ実際の局はわるいので、ダミーロードで動いている机の下のレピーターにアクセスしてみます・・・・
あれ、受信弱すぎ・・。フルスケールで入るハズだがSが2-3くらいしか振らない。天井裏にももう一台ダミーロードレピーターがあるのでこっちでも確認。やっぱり駄目。実際に外部のレピーターアクセスすると、いつも強かった局がカスカスとか、非常に弱い。
あーこれは受信も MD004H の不具合でぶっ飛んだなとすぐ解りました。この辺はツイッターやFaceBookでボヤいていますが、MD004Hの切り替えが壊れてうまく切り替わらないのに送信を繰り返した為に送信電波の一部が MD004Hを伝って受信初段のMGF1302に流れ込み破壊したものと思われます。
しかもこの MGF1302これも生産して居ないFETで探しても見つからない。これも eBay の UK にありましたが購入が非常にめんどくさいので放置。eBayにはMGF1302(偽物)のめっちゃ安物が(Made in China)は沢山ある。しかし中国製はロクなものは無いので除外。その後いろいろ探していのですが、MGF1302は見つからず。ヤフオクでも出てこないので半ば諦めていたんですが、他で代用できないかと探したところどうやら 2SK571で代用出来ることもわかりました。しかし探してみるとこれもなかなか無く、秋月には PDF のデータシートだけ存在し部品自体はなかった。探し回ってやっと若松通商にあるのが判明し急いで購入。無くしてもアレなんで2個購入しました。
MGF1302と2SK571はピンの配列でD(ドレイン)とG(ゲート)が違うのでS(ソース)を基準に入れ替えます。MGF1302と2SK571の取付方向が違うのが写真でおわかりいただけると思います。
 |
 |
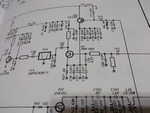 |
購入した2SK571 |
交換前MGF1302 |
MGF1302周辺回路 |
 |
 |
 |
MGF1302裏面 |
2SK571に交換 |
今回交換した部品 |
ここまで来るのに半年ほどかかっちゃいましたが、一応修理完了としたいと思うのですが、内蔵電源がまだ修理完了していません。こちらは直流ではショートしないので交流を流したときに短絡するようなので、たぶんコンデンサ周りかんとは思います。こちらは追々やっていきます。現状外部電源で動作していますので全く問題ないので。
そして、受信ですが以前と変わらないほどに回復しました。ローカルさんともまともにお話しも出来るので問題ないようです。本体が終わったので後は内蔵電源の修理かなと考えて居ますが、DCで使えてしまっているので、その内の様な気もします。
内容としてはツイッターやFBと重複してしまいますが、一部公開して居ない写真なんかもUP致しました。追々最初にリンクしたページに追加して行きます。
ここまで書いてなんですが実はこれと同時に予備で使用していたIC-2500が送信出来なくなってしまいました。こちらも再度修理していきます。ただ状況としては、熱を持つと送信せず、冷えた状態からは出るようなのでまだ故障探求までには至っておりません。
以上です。
IC-1275交換修理まで ⑤
IC-1275、5回目の掲載です。前回は IC と トランジスタとスピーカーを交換をするということで無事部品も到着したので作業再開です。
 |
今回到着した部品(写真1)とりあえずμPC577とその周辺のトランジスタとダイオードも注文したので該当部品を外してチェック。μPC577は新品と確認してみたけどテスターで当たっただけでもう既に値が全く違うので、これはもう飛んでると判断。その他の部品は問題ないですが、予防交換で全て新品に交換します。 そして前回の続きで、触診。見つけた損焼跡のある箇所を調べたところ、Q54 2SD468 ものすごく熱い。これがどうも飛んでいるようで、確認の為、周囲のトランジスタと一緒に基板から外してチェック。予想通りそのトランジスタが飛んでました。これは注文した部品から外れてしまったので買い直しです。秋月電子にこのQ54 2SD468の在庫があったので、バックライト用の電球色LEDとともに再購入となりここはまた延期・・・となりました。 ちょっと時間が掛かりましたが、やっと2SD468来ました。残念ながら日本製じゃなさそうなのでちょっと不安もありますが、とりあえず外した部分に装着。見たところそこ以外は別段問題もなさそうです。でもこの後にさらなる試練が待ち受けておりました。(これは後述します) 到着した2SD468(写真2)と交換した箇所の回路図と場所(写真3)。Q55とQ53(赤線に消えてますが)それとQ54とQ52が該当するトランジスタです。実際はQ54が飛んでいましたがここは、Q55+Q53で受信時に+8を作り送信時は0Vとなる回路、Q54+Q52は送信時+8Vを作り、受信時は0Vとなります。あちこちに供給しているようです。 ちゃんと音声出ます。やっと終わったーと思った矢先のこと・・・。 話はちょっと変わります・・・ 先日、みちびきの2号機打ちあがりましたね。これでまたさらに1200MHz帯が危うくなってきました。もともとアマチュア業務は2次なので1次の業務を邪魔しないのが一応決まりです。リピーターも10Wは許可にならないとか。いろいろ騒がれていますね。JAXAさんのみちびきのblogでもこのレピーターの電波がかなり、ネックになっているらしく、JAXAさんなりにANTを低くしたりいろいろ頑張ってる見たいです。 1200MHzや2400MHz等で勘違いされている方多いようですが、アマチュアが優先とか先に使ってるんだからとかはまったくもって問題外ですのでご注意を。これ以外のBANDでもありますので十分注意して下さい。 アマチュアは2次業務です。1次の業務優先となるので大手を振って妨害するのはやめましょう。電波法違反になります。 話を戻しまして、ここである事に気がつきます。BUSYが点灯しない。まぁこれぐらいはどーでもいいかと、そしてモニターしながら送信してみるとあれ?変調が乗らない・・・・。ボリュウム関連かと色々確認しましたまが違うようです。 ブロックダイアグラムを見ると、マイクから 2SC1571で増幅してるようなので、まずコレクタにオシロ接続すると波形出ていません。このトランジスタを交換しようとwebで探してもありません。既に廃品種になっているようです。仕方なく互換製品を検索。そうすると 2SC2240で代用出来ることがわかりましたので、2SC2240に交換。すると今度はうその様に気持ちよくオシロの波形が出ます。(末尾の規格表参考に) それでも音声が乗りません。そう簡単に治させてくれません(苦笑)。そして順に追っていくと、MICゲインのボリュームに行っている所で波形が一切出ていない事が判明。はぁなんだろー。とブロックを眺めてるとMICゲインに行く前に変な Mute回路が組まれています。IC375のサービスマニュアルの回路説明を読むと、受信時は Muteになっていて、MIC回路はGNDに落ちる回路になっているらしい。なんかこれ、とっても怪しい。で、試しにQ38のベースとグランドの導通を計ると送受信ともに「ショートしてますよー」状態。Mute回路のトランジスタQ38のRN1202と言う複合トランジスタがショートしてるみたい。(写真6)特に抜いてもとりあえずは支障なさそうなのでこのトランジスタを試験的に基板から抜いて、モニターしながら送信すると音声出た。 前段Q70のRN2204も怪しいのでまとめて交換です。複合と言っても、抵抗が入ってるだけで、ちょっとまともには値は出ませんがQ38が短絡してるっぽいようでした。とりあえず元に戻して、電源を入れ送信テスト。めでたく音声が出ました。と、同時に BUSY ランプもちゃんっと点灯する様になりました。 |
写真1 |
|
 |
|
写真2 |
|
 |
|
写真3 |
|
 |
|
写真4 |
|
 |
|
写真5 |
|
 |
|
写真6 |
最後にバックライトの交換です。75シリーズは最も難易度が高いです。フロントパネルにケーブルをつけたまま交換は、ほぼ無理です。修理されている方は苦労されているようでやはり私と同じ方法で交換している方が多い様です。こんな事を一度もやったこと無いとか、初心者の方、慣れていない方はやめた方がいいです。
 |
 |
 |
写真7 |
写真8 |
写真9 |
 |
 |
写真10 |
写真11
|
こんな感じです。見たとおりものすごい数のケーブルとコネクタがあります。写真7はケーブル類をコネクタから外してシールド板がネジ止めされているのでそれを外した写真になります。結構な数のネジで止まっています。これはもう本体から切り離す寸前です。コネクタは、フロントパネル側を外しますが、シールド板を外さないと取れない物もあり、実際は本体側のPLLユニット(写真8)を開けて取らないと外せないのが数本あります。
写真9はLED化した後で外した電球が左上に見えています。LEDですので直接12Vを掛ける訳にいきませんので、最大13.8Vが流れる事を考えて電流制限抵抗を取り付けます。取り付けるLEDの種類で抵抗値を決めます。もちろん抵抗をつけるスペースはありませんので写真の様に立てていますが、シールド板が入りますので抵抗の足がショートしない高さに調整します。(言ってる意味が解らない人はやらないでください)
写真10と写真11は点灯テストの写真。ワニ口で電源SWに行っているコネクタにDC12Vを印加します。綺麗に点灯する事を確認します。ここで逆接とかしないでくださいね。壊れますたぶん。
 |
 |
 |
写真12 |
写真13 |
写真14 |
これでだいたいの修理が完了です。全て元に戻す行程です。コネクタ類はコネクタに刻印が印字されているのでわかりやすいと思いますが、同じサイズのコネクタの誤挿入だけは注意してください。
誤挿入しそのまま電源を入れてしまうと壊れる場合がありますので十分確認してください。「たぶん大丈夫」だとか「心配ない、心配ない」と言う根拠の無い安心はしないように。元に戻します。電源をONにして動作確認。(写真12)
余談ですがマイクにパッチンコアがついています。(写真13)これはHFが回り込むとかというわけでは無く実はここ1Km先に50Kwの STV ラジオの送信所があり、変な接続をすると、大抵の方はNHKが聞こえるのですが、うちは STV が聞こえてしまいます・・・。なのでイモハンダとかは御法度になります。そこがダイオードになり、無音になるとコマーシャルやトークが聞こえてしまいます。酷いと目的外通信に取られかねますのでみなさんも注意しましよう。(なるのかなw)
写真14は今回交換した全ての部品です。
型名 |
社名 |
用途 |
構造 |
最大定格 Max. Ratings(Ta=25℃) |
電気的特性 Elec. Character.(Ta=25℃) |
外形 |
備考 |
||||||||
Minf. |
App |
Type |
VCBO |
VEBO |
Ic |
Pc |
Tj |
直流又は |
VCE (V) |
Ic (mA) |
fab/ft* |
Cob |
Pac.Dim No. |
||
(V) |
(V) |
(mA) |
(mW) |
(℃) |
(MHz) |
(pF) |
|||||||||
2SC1751 |
三洋 |
LN |
Si,EP |
40 |
5 |
100 |
200 |
125 |
160-960 |
6 |
1 |
100* |
3 |
138 |
|
2SC1681 |
東芝 |
LN |
Si,EP |
60 |
5 |
50 |
200 |
125 |
450 |
6 |
2 |
130* |
NF=3dB(F=10Hz) |
33 |
|
2SC1755 |
三洋 |
PA |
Si,TP |
300 |
7 |
200 |
15W(Tc=25℃) |
150 |
40-200 |
10 |
10 |
>50* |
<5.3 |
268 |
|
2SC1843 |
日電 |
RF,LN |
Si,E |
60 |
100 |
250 |
125 |
400 |
6 |
1 |
110* |
3.5 |
138 |
||
2SC2240 |
東芝 |
AF,LN |
Si,E |
120 |
5 |
100 |
300 |
125 |
200-700 |
6 |
2 |
100* |
3 |
138 |
|
2SC2320 |
三菱 |
AF |
Si,E |
50 |
6 |
200 |
300 |
125 |
90-800 |
6 |
1 |
200* |
2.5 |
138 |
|
2SC2634 |
松下 |
AF |
Si,EP |
60 |
7 |
100 |
400 |
150 |
180-700 |
5 |
2 |
138 |
2SA1127とコンプリ |
||
2SC1815 |
東芝 |
AF |
Si,E |
60 |
5 |
150 |
400 |
125 |
70-700 |
6 |
2 |
>80* |
2 |
138 |
2SA1015とコンプリ |
2SC945 |
日電 |
RF,AF |
Si,E |
60 |
5 |
100 |
250 |
125 |
200 |
6 |
1 |
250* |
3 |
138 |
2SA733とコンプリ |
IC-1275検証 ④
さて、先日ばらしたIC-1275ですが、一時的に組み立て直して、チェックしてみました。ただ、残念ながらサービスマニュアルは未だありません。しかし丁度いい感じに、IC-375のメイン基板がほぼ同型をしているようなので参考にしました。定数は若干違うのと、10/50Wタイプでチェック電圧が多少違うくらいでしょうか。でもおおまかな流れがつかめるんじゃないかなと。そして触診していると一発めでものすごく発熱している部分を発見。
 |
 |
 |
(左の写真)丸をしている部分のICです。μPC577Hです。IC-375の回路を参考にして電圧を測定するとこの周りの測定をするとどれ一つとして電圧が出て居ないことがわかりました。この周りにはトランジスタ3個とFET1個そしてこのIC。後はダイオード。でもどれもこれも超怪しい訳です。測定すると、どのポイントも、ほぼ0Vなので何かがぶっ飛んでショートしているらしい。一応基板に刺さったままだけどトランジスタのショートを確認したけど割にちゃんと動いているっぽい。FETもGNDに落ちているもの以外は短絡形跡なし。目安にしかならないけど、表示している電圧には全くなっていない。まぁ外してみないと正確にはわからないけど・・・。(真ん中の写真の回路がこの辺です)
このサービスマニュアルの通りの電圧にはならないとしても、0Vはないと思う。なんかもうこのICのような気もしないわけでもない。そしてこのICがものすごく熱い。こいつが悪いのが周りがわるいのか・・
そして、この横の長いアルミのヒートシンクにぶら下がっているICが定電圧ICの7808。これはきちんと出力が 8V 程出ていたので問題なさそう。(前回の丸印の一つ)、もう一つ
2SB596がついている。こちらはまだ未チェック。
とりあえずこのμPC577Hと周りにある、2SC2785とRN2202、2SA1048をまず交換して見てから?なのか、まだほかに原因があるのか、全てチェックしていないのでもう少しデータを取ってから部品は注文しようかと考え中。でももしかしたら電解コンデンサやセラミックコンが短絡してる可能性もあるから、この周辺は丸ごと交換?
そして壊したSP(右の写真)ですが直径65mmスピーカーないないって騒いでいましたけど実はすぐそばに大量に有りました(苦笑)しかしこのSP、コーンがプラなんで音がどうなのかな?なんて言う心配も。このSP、実は会社で捨てると言う物品の中にこのスピーカーが10個ほどあり「ラッキー」と思いながら持ってきました。ぴったりはまりました。純正のSPはどうやって固定していたのかわからなかったのですがなんと、単に後ろを両面テープで
貼り付けていただけと言う・・ただ今回のスピーカーは純正と違って高さがないので両面テープと言う技が使えない・・・
考えた結果、縁に小さく切った強力な両面テープを貼り、それに貼り付けて固定する事ができました。とりあえず少しだけ進みました。音も出して見ましたがまぁあまり気にはならないと言うかBEEP音しかまだ聞こえないのでなんとも言えませんけど。残念ながらこの時既に、受信すらしない状況になっておりました。
なんだかんだと、とりあえず少しだけ光が見えた様な気がします
今度は受信が出来ない(時々) ③
先日修理した IC-1275 、前回書いたと思いますが今度は暖まると受信が出来なくなってしまう。と言う症状に襲われています。送信は出来ているので受信系だって言うのはわかるのですが・・・。
いかんせん、サービスマニュアルが無いので調整すら出来ません・・・。
とりあえず該当する基板を引っぱがして見てみました。
 |
 |
 |
これ問題の基板 |
赤丸2カ所が異様に焼け |
ばらばら中 |
こんな感じになっています。赤丸2カ所が原因とは限らないのですが・・。
もしかすると受信の際にPLLがUNLOCKと言う選択肢も有るわけです。トランジスタは 2SC2785 と RN1202やRN1204、2SD468も見えています。ヒートシンクにへばりついてるトランジスタも怪しいのですが、とりあえずこの辺をばらばらっと交換してみようかと思っています。
もちろん抵抗やコンデンサも確認しようかと思っています。裏の半田面ですがざっと見てクラックは見つけられず・・・。夜にやる作業じゃないと思いますが・・・とりあえず前段階です。
何年かかるのかなwファイナル交換で1年以上ほったらかしにしてましたからね。そのおかげでスピーカーのコーンが破けました。破けただけならのりで貼り付ければいいかもなんですけど一番大事なコイルに行くケーブルが切断されてしまいました(苦笑
65mmのスピーカーってなかなかないんですよねぇ。0.2W ならみつけましたけど・・・。それも一緒に修理予定です。
パワーモジュール交換 ②
IC1275のファイナルが飛んだのではないかとそのまま放置で1年過ぎてしまいました。ついこの間だと思ったのですが1年以上経過していますね。結局ファイナルっぽいようでした。ファイナル・モジュールを注文する機会があまりにもなく放置でしたが、先日ショップに行ったついでにメーカーから取り寄せていただきました。しかし残念ですがICOMは1200MHzの無線機を製造しなくなりましたので、モジュールの廃品種になるのは近い将来間違いないと思います。今回はモジュールだけ交換とようと思いましたが、メインダイアルを回すと UP しかしない現象も写真は撮っていないのですが併せて修理いたしました。
 |
 |
 |
ショップで購入 |
SC-1040 |
外したSC-1040 |
今回購入したものと、付いているモジュールをはずして見てみると若干形が変わっています。とくに対戦には影響は有りませんのでそのまま作業は続行です。ロゴも無くなってますね。古いロゴですが無線機自体は新しいロゴです。この上に乗っている中継兼ヒートシンクが結構曲者です。
 |
 |
 |
足の長さ確認をします。 |
適当な長さに切断して |
最後は元に戻しておしまい。 |
FBが入っているので該当するピンにFBを戻して足をカットして元に戻します。まぁいつもの通り自分でやってますが、実に信用が有りません。(苦笑
ひとまずバラックで組みたてて、パワーONにし、電波が出るか確認・・。出力にはダミーが付いていますのでとりあえず問題なくパワーは出てるみたい。そして本格的にくみ上げる前に、VFOの不具合調査。
1.VFOを回すとダイアルが重たい。
2.UPしかしない。(MICのUP/DNは効くのでLogicでは無くロータリーエンコーダーっぽい。)
ばらすに当たってあちこち汚いので清掃しながらとなりました。エンコーダーの部分は触ったことのない人はやめておきましよう。
まずダイアルの重たい感触は、ちょっと注油をしてやると軽くなりました。ただ間違っても CRE556を使わないように注意して下さい。
あれは研磨剤も入ってますので、使うと間違いなく軸にガタが来ます。純粋に油を差しましょう。私はいいのが無かったのでミシン油を
注ぎました。「チョンチョン」と大量では無くごく少量です。大量に注油すると、後からしたたり落ちますので。
エンコーダーの部分も電圧もきちんと出ていましたのでこの部分じゃなくメカみたいで、あけてみると薄い穴あきの鉄板が変形していた
のでねじをゆるめて少しのばし気味にしてみた。
元通り組み立てて電源ONで最初電波が出なくなって、なんかやらかしたのかと思って再度ばらしてみたけど問題はなく、よく見ると
正面パネルのATVがONになっていた・・こりゃでんわ・・。
原因解ればあとはすぐ。電源をいれVFOを回すとちょっとぎこちない動きはするけど運用には問題ない程度の回復を見た。ぐるぐる回してもちゃんとUP/DNするし、MICでもOK。ホントに電波出てるかはローカルが出てこないとわかなんないけど、多分大丈夫でしょう。麦球も片方切れてしまったけど、時間があればLED化しようと思っています。でもこの手のパネルは裏のシールドパネル取るのが結構難儀だったりしますがまた次回・・・。(いつになるのか・・
IC-1275の修理履歴 ①
全盛期時代に購入したIC-1275の終段(出力モジュール)が飛びました。かすかに電波は出ています。Bird43の 1.2Gスラグ25Wフルスケールでねちょこっととしか出ていません(苦笑)
Bird43の目盛りが・・ |
こんな感じでございます。先日ローカル局と話している最中に、不穏な動きが感じられたのでパワーメーターを見ると内蔵のメーターもpowerが出ていないよって振りをしていました。なんかしたかなと、パワーコントロールやあちこちスイッチをいじってみましたが状態変わらず。異常に本体が熱いので熱暴走かといい加減冷やしてから再度電源投入し、送信いたしましたがやっぱり変わらず。仕方なく内部をばらすとゴムが溶けてダラーと流れていたのを筆頭にほこりまみれになっていたのを多少清掃。製造から何十年と経過していますので、半田のクラックかなと疑ったのですが、パワーユニットを覗くもその形跡は無く、念のため半田を盛り直してみました。モジュール部分の半田のこぼれは私ではありません(苦笑)製造当初より
 |
 |
 |
電源ユニット+Powerモジュール |
電力増幅部 |
Powerモジュール付近 |
と言うことで今のところモジュールなのか、全段・・なのかはまだ調査しておりません。それとは別にVFOが右に回しても左に回してもUPしかしないと言う特有の現象と、ダイアルが重い。追々治していきたいと思います。取りあえず次の行程は別基板の確認ですな。それから順に追っていきたいと思います。
履歴
2021/04/01 写真のリンク切れ修正
2020/05/07 順番入替・⑥追加
2017/07/16 ④,⑤追加
